第2回は一次試験対策について書いていきたいと思います。一次試験合格済みの方は、次回以後の二次試験対策の記事を楽しみにしていただければと思います。
試験までのスケジュールを考えると、一次試験対策の記事を書くことができるのは、今回だけになってしまいますので、少々長い記事ですが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
試験勉強において意識しておくこと
資格試験の勉強においては、試験合格というゴールを意識した勉強が重要になると考えています。
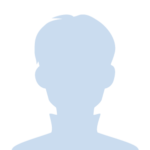
勉強のゴールを意識していますか?
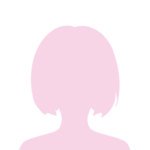
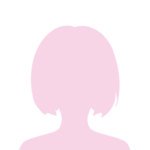
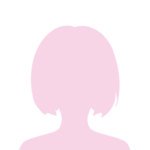
毎日忙しいし、勉強するだけで時間がなくて、ゴールなんて意識する余裕がなかったです。
読者の中にもこのような状況の方もいらっしゃるのではないでしょうか。このような場合、ただ闇雲に勉強をしていないか、一度振り返ってみる時間を作ってはいかがでしょうか。
何事に対しても言えることですが、進むべき方向がわからないままただ闇雲に走っている人と、ゴールを意識して進むべき方向が明確になっている人、どちらの方が短時間で成果が得られると思いますか?
言うまでもないですが、ゴールを意識して進むべき方向が明確になっている人の方が、いい成果を得られるはずです。
一次試験の勉強の始め方
すでに勉強を始めていらっしゃる方が多いと思いますが、これから始めるという方は、ここから読み進めていただければと思います。
まず初めに、合格というゴールをもう少しブレイクダウンしてみましょう。
一次試験のゴールから逆算した目標設定(私の場合)
ゴール:一次試験合格
▼
7科目420点以上 or 科目合格の場合は全教科60点以上
▼
数学的・論理的科目は得意、丸暗記が必要な科目は苦手で、差が大きいので7科目一発合格を目指す
▼
7科目目標:安全率を考慮し440点を目指す&苦手科目の足切りは絶対に回避する
▼
科目ごとの目標
得意な2科目は70点、苦手な2科目は55点、それ以外は65点を目指す
このようにすることで、苦手科目について多くの時間を割き、無理して60点以上を目指す必要がなくなります。
結果として、全体のパフォーマンス(今回の場合は7科目の合計得点)の向上を狙うことができます。
副次的な効果として、目標値に余裕を見ていることで、本番で多少失敗しても問題ないというマインドになれます。
テキストの選び方
アドバイスになりませんが、テキストは何でもいいです。自分自身が気に入ったものであれば本当に何でもいいのです。
長期戦の試験勉強においては、モチベーションの維持は必須です。
気に入ったテキストを相棒にすることは非常に重要なので、ネットで買うのはあまりお勧めしません。
書店でパッと手に取って気に入ったものをお勧めします。
その一冊(一式)を使い倒してください。
試験勉強の最中に迷いが生じて、ほかのテキストに浮気したくなることもあると思いますが、以下のようにデメリットがあると考えています。
- 学習内容が重複し、無駄な時間を過ごしてしまう。
- すでに知っている部分を学習して、勉強できるようなつもりになってしまう。
- テキストの体裁が異なっていて、読むのに時間がかかってしまう。
- 結果として、問題演習に取り組む貴重な時間が無くなってしまう。
テキストを選んだ理由(私の場合)
私は「みんなが欲しかった」シリーズを使用していました。選んだ理由はシンプルですが以下の通りです。
- 分量が多すぎないため、挫折せずに頑張れそう
- 分量が少なすぎると、不安になりそう
- 図が多く見やすい
- テキストにも例題や練習問題が多く、学習と復習のサイクルを回すことができる(詳細は後述)
一次試験勉強での知識インプット方法
勉強は過去問から?テキストから?
最初に過去問を解くことから始めることを推奨する方も大勢いらっしゃって、どこから勉強を始めるか迷ってしまう方もいらっしゃると思います。
しかし結論から言うと、どちらから先に始めても構わないと考えています。
ただ、次のような注意点がありますので、勉強の際には意識しておいていただければと思います。
- ゴールは問題を解けるようになること
- テキストを使った知識のインプットは手段
- 問題を解けるようになるためには、問題演習を繰り返すことが必要
迷っている時間はもったいないので、過去問1年分を解いたり、テキスト1科目分流し読みしたりして一歩先に進むことで、見えてくるものがあると思います。
インプットを重視しすぎてはいけない
知識のインプットは必要ですが、時間が有限である限り、それに特化しすぎてはいけないのです。
では、なぜ問題を解けるようになるために、インプットを続けてはいけないのか。
能動的学習
学習の効果は、読書のような受動的なものよりも、他人に教えたりする能動的なものの方が深く理解できると言われています。
- 教科書を読むだけでは頭に入ってこない
- 問題を解いたり、主体的に疑問に思って調べることで初めて頭に入ってくる
- 自分の解答の理由や解答プロセスを説明できるようになると、更に深い理解が得られる
また、深く理解できるというところがポイントです。関連知識などを自ら調べてインプットするところまでできれば、次のような効果も期待できます。
※ただし深入りしすぎて脱線しないように注意しましょう
- 関連知識を頭の中でリンクさせた状態で記憶できる
- 紛らわしい用語の使い分けもセットで把握できる
転移適切性処理説
転移適切性処理説とは、語学の学習における理論です。
(私は『最新の第二言語習得研究に基づく 究極の英語学習法』という本で知りました。)
英語のリスニング能力は、英語のリスニングを行うことで最も効率的に鍛えられる。
当たり前のように思いますが、この理論を忠実に実践できている人は少ないのではないかと思います。
そして、私は試験勉強においてもこの理論が適用できると考えています。
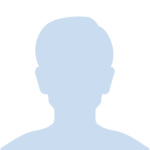
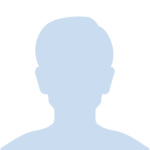
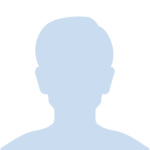
問題を解く能力は、問題を解くことで最も効率的に鍛えられる。
これは二次試験対策でも非常に重要な考え方になります。(詳細は夏頃に執筆予定の二次試験対策の記事にて。)
勉強方法(私の場合)
勉強の順番
おおまかに以下のような順番で取り組みました。
- テキストを流し読み
- テキストの例題の演習+復習
- 問題集の演習+復習
- 過去問演習
ネット検索をフル活用して、周辺知識を含めて体系的にインプット
また、自分用の復習メモのようなものは作りませんでした。
問題演習に取り組む時間が重要だと思っていたため、短時間で非常に広い試験範囲を網羅したメモを作成することができないと判断したからです。
勉強の順番を決めた理由
以下のような理由でこのような勉強の順番で取り組みました。
- いきなり過去問を見ても全然解けない
- 用語を知らないから問題の意味が分からない
- 解けない/わからないと、モチベーションが下がる
一次試験での過去問演習方法
過去問演習の目標
勉強の初期段階では、ゴールから逆算して目標をブレイクダウンして考えました。
過去問をしっかり解き始める時期になると、当然目指す目標は変わってきます。
当然ですが、7科目一括で受験する方は、7科目合計の得点が最重要になります。過去問演習の場合は各科目の得点は気にせず、7科目合計でどのくらいの得点となっているかまで考慮することが重要です。
7科目一括で合格を目指す場合
目指すところは変わりませんが、とにかく足切り回避と7科目の合計点を高めることです。
これまでにテキストや例題を用いて勉強をしてきた方は、過去問をベースとしたテキストの内容に触れているはずなので、すでにネタバレのような状態になっています。
少し目標得点を高めに見ておく方がいいでしょう。
- 足切り回避
40点台の科目があれば、50点以上になるように目指す
50点台の苦手科目は無理して60点以上を狙わない - 合計得点を高める
得点を高めやすそうな科目に注力し、7科目合計で450点を目指す
得点が伸びにくそうな科目には無理に注力しない
科目合格を目指す場合
やることはひとつ、非常にシンプルです。
60点以下の科目があるといけないので、ひたすら得点が低い科目の底上げを図るのみです。
当然ですが、科目合格を目指すのに、得意科目ばかり勉強していると、苦手科目で合格できません。
復習の方法
当たり前のことですが、復習は大事です。
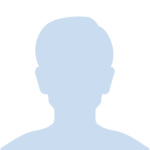
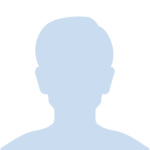
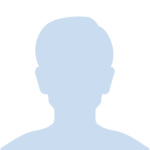
間違えた問題はしっかり復習しましょう。
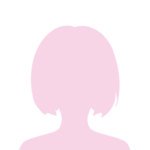
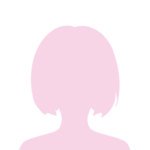
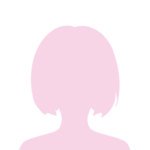
言われなくてもやってるよ!
もちろん、多くの方が復習に取り組んでいると思いますが、効果的な復習に取り組めているでしょうか。
記憶の定着のためには、次のような点を意識した復習を行うことが良いとされています。
- 復習は1度ではなく複数回行う
- 復習のたびに、復習する間隔を長くしていく
ただし、最初から間隔をあけてしまうと、記憶の片隅にも残っていない状態になる可能性もあるため、私は以下のように取り組んでいました。
- 問題を解いた直後(翌日まで)に復習する
- 約1週間後に再度問題演習を行い、その後見直す
一部の短期記憶が優秀な方にとっては、無駄なプロセスになると思いますが、多くの一般的な受験者にとっては、復習をすることにより、確実に問題を解けるようになっていくことの積み重ねは非常に重要です。
まとめ
一次試験は基本に忠実に取り組むことができれば、超難関の試験ではないと考えています。
改めて、以下のポイントを意識して、より効率的な勉強方法を探してみてはいかがでしょうか。
- 試験勉強ではゴールを意識する
- 問題(過去問)演習の時間を十分に確保する
- 過去問に関連する知識などは積極的に取り入れる
- 復習は徹底的に行う











